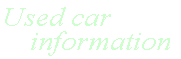ホンダ:アコード中古車情報!カタログ・在庫
|
|
中古車在庫情報・カタログ情報や最新ニュース、オーナーの口コミなど♪ ホンダ:アコードの概要♪初代 (1976-1981年 SJ/SM型) 
1976年5月7日に、中型の3ドアハッチバック車として登場。3BOX4ドアセダンは、1977年10月14日に発売された。 1978年9月1日には、53年排出ガス規制をクリアしたEK型 1.8L 直列4気筒 CVCC SOHCエンジンを搭載。また、最上級グレード「EX」には、当時の国産車では珍しかった車速感応型パワーステアリングが標準装備され、その後追加された「EX-L」にはパワーウインドウが、1800サルーン「EX-L」にはフルオートエアコンが追加された。1800サルーンのダッシュボードはトレイのないデザインとなっている。 1979年10月にはホンダマチックを「OD-☆-L」の3速セミオートマチックトランスミッションに改良し、パワーステアリングを装備した1800サルーン「ES」が追加された。 1980年4月25日にはエンジンがCVCC-IIにバージョンアップと同時にサルーンは角目4灯式ヘッドライトにデザインが変更された。パワーアップとラピッド・レスポンスコントロールシステムによる運転性の向上が図られた。 1980年7月にはクイントと同じ90PSのEP型 CVCC-IIエンジンを搭載する1.6Lモデルが復活した。 2代目 (1981-1985年 SY/SZ/AC/AD型) 
1981年9月22日にフルモデルチェンジ。搭載エンジンは、EP型 直列4気筒 CVCC II SOHC 1.6LとEK型 直列4気筒 CVCC II SOHC 1.8L。同時に姉妹車のビガーが誕生した。オプションで、前後の荷重変化による車高変化を修正し、2段階の車高変化が可能な「オートレベリングサスペンション」を装着できた。クルーズコントロールは全グレードに装備され、操作スイッチはステアリング・ホイールに取り付けられた。また、世界で初めて民生用カーナビゲーション(自社開発のガスレートジャイロ方式)がメーカーオプションとして用意された。 1982年11月3日に、一部変更。ホンダマチックは4速フルオートマチックへ改良された。 1983年6月17日にマイナーチェンジ。直列4気筒 CVCC II SOHC 12Valve クロスフロー エンジン(EY型:1.6L , ES型:1.8L)を新たに採用。日本車初となる4輪ABSを搭載しており、当時は4wA.L.B.という略称があった。 1984年5月24日に、1.8L PGM-FI仕様エンジンが追加された。このエンジンはCVCCでは無い。 3代目 (1985-1989年 CA1/2/3/4/5/6型) 
1985年6月4日、セダンをフルモデルチェンジ。国内、北米、オーストラリアモデルはリトラクタブル・ヘッドライトを採用し、ヨーロッパモデルは、セダンが異型4灯式ヘッドライトを採用した。 搭載エンジンは、新開発の直列4気筒 DOHC 16Valve 1.8L CVデュアルキャブ仕様のB18A型と2.0L PGM-FI仕様のB20A型及びSOHC 12Valve 1.8L シングルキャブレター仕様のA18A型で、1987年のマイナーチェンジの際に2.0L シングルキャブレター仕様のA20A型が追加された。北米はA20A型 キャブ/PGM-FIのみ、ヨーロッパは、A16A型キャブ、A20A型 キャブ/PGM-FI、B20A型PGM-FI、オーストラリアは、A20A型 キャブ/PGM-FI。全てCVCCでは無い。B20A型は、シリンダーヘッドだけでなく、鉄製が主流だったシリンダーブロックもアルミニウムで、エンジン重量あたりの出力効率は当時の世界一を記録した。 サスペンションには、レーシングカーやスポーツカーが採用する4輪ダブルウィッシュボーンをFF量産車として初めて採用。ボディーデザインはフラッシュサーフェス処理により空力に優れ、cd値=0.32を達成した。1985年日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞している。 1985年7月20日、ハッチバックがフルモデルチェンジされ3ドアワゴンのような形になり、エアロデッキとサブネームが付けられた。搭載エンジンは、B18A型、B20A型及びA18A型キャブレター仕様。ヨーロッパではA20A型 キャブ/PGM-FI仕様が販売された。北米、オーストラリアではエアロデッキとは異なるファストバックタイプの3ドアハッチバック仕様が用意され、エアロデッキは販売されなかった。 1987年5月に国内モデルをマイナーチェンジ。大型バンパー、カラードドアミラー、リアコンビネーションランプの意匠変更、B20A型のヘッドカバーの金から黒への塗装色変更、2.0Lモデルのブレーキローター径の変更、ATの改良、インテリアトリムの変更、電動格納式ドアミラーの追加等が行われた。 1987年7月3日に、ヨーロッパ向けに販売されていた薄形異型2灯式ヘッドライトを装着した、アコードCAの販売を開始。「CA」とは「CONTINENTAL ACCORD」を意味する。欧州市場でも、エアロデッキはリトラクタブルライトを装着し販売された。 1988年4月8日に、北米で開発及び生産された、アコードクーペ(左ハンドル仕様)の国内販売が開始され、海外の日本車工場の乗用車を輸入して販売するのは、これが史上初めてとなった。搭載エンジンはA20A型 PGM-FI仕様のみ。同時に薄形異型2灯式ヘッドライトのアコードCAにも、DOHCエンジン搭載車が追加される。 1988年9月の一部変更では、ATにシフトロックシステムが追加され、同時にエアコンを標準装備して価格を引き下げた「スーパーステージ」が追加される。
発売後、旧ホンダ店がクリオ店とプリモ店に分割され、のちにアコードはクリオ店専売車種となるが、このモデルまでは経過措置としてプリモ店でも併売されていた(ただし「CA」はクリオ店専売車種だった)。逆に、のちにプリモ店専売車種となるシビックも同じ理由で1987年まではプリモ店とクリオ店の併売だった。 4代目 (1989-1993年 CB1/2/3/4型) 
ボディバリエーションは、初代から続いていた3ドアハッチバックが廃止され、サッシュドアを用いた4ドアセダンのみのラインナップだったが、後にアメリカ・オハイオ州HAM生産のクーペとワゴンが加わる。 スタイルは先代のキープコンセプトだったが、サイズは5ナンバーフルサイズとなり、キャビンも全高がとられたことによって居住性が向上した。サスペンション形式は先代同様四輪ダブルウィッシュボーン式サスペンションだが、この代はストロークが増やされ乗り心地や路面への追従性が向上した。バブル期に開発されたことから、ボディには当時、アウディが取り入れ始めた亜鉛メッキ鋼板を広範囲に渡って使用し、室内の内張りの素材も音がこもりやすいフロアやルーフには新開発のハニカム構造の防音材を採用し、触感も考慮された。スタンレー電気と共同開発したマルチリフレクター式ヘッドライトが採用され、バルブのみが取り替えられるタイプに変更された。 エンジンはアルミ合金ブロックの新開発F型に変更され、全車4バルブ化された。1.8LはSOHC 電子制御キャブ仕様のみ、2.0LはDOHC/SOHC PGM-FI仕様とSOHC 電子制御キャブ仕様のラインナップだったが、後にHAM産のワゴン、セダン及びクーペに2.2L SOHC PGM-FI仕様が追加される。 トランスミッションは、全グレードともに特徴的な7ポジションの4速ATと5速MTが用意されたが、2.0L SOHC仕様とアメリカ産のクーペ、ワゴンは4速ATのみだった。 このモデルからアコードはクリオ店専売車種となりプリモ店では取り扱われなくなったが、代わりにプリモ店専売車種として姉妹車のアスコットが同時発売された。 国内販売は振るわなかったが、アメリカではフォード・トーラスを抑えて、3年連続して全米トップセールスを記録している。 5代目 (1993-1997年 CD3/4/5/6型) 
衝突安全基準MVSSの影響を受けて、全車3ナンバーボディとなる(全幅1,760mm)。いすゞ自動車へアスカとしてOEM供給される、これは6代目アコードまで継続した。欧州ではアスコット・イノーバベースのセダンが引き続き販売された。 ボディラインナップは4ドアセダンに加え、後にアメリカHAM産の2ドアクーペと5ドアワゴンが加わる。長は先代よりもわずかに短く抑えられているが、室内空間は先代とおおきな変化がない。 エンジンは全機種、電子制御インジョクション化され、トルク、パワーともに向上した。主力モデルのF22B型
2.2L SOHC、F20B型 2.0L SOHC、F18B型 1.8L
SOHCの他、スポーツグレード用のH22A型 2.2L
DOHC がラインナップされ、2.2LはVTEC化が施された。 アメリカ市場を重視した設計のため、5ナンバーの国内専用車種 アスコット(2代目)/ラファーガを発売したが、結果はそれらのモデル以上の販売成績をおさめ、先代よりも堅調な売れ行きを示した。 6代目 (1997-2002年 CF3/4/5/CL1/3型) 
このモデルから世界共通フレキシブルプラットフォームを採用し、地域別に違うボディサイズで生産する方針をとったため、日本仕様は4代目以来の5ナンバーボディが採用されるが、スポーツグレードの「ユーロR」とワゴンはフェンダー幅が若干拡げられ3ナンバー登録となる。 ボディはサッシュドアを持つ4ドアセダンと5ドアワゴンがラインナップされるが、キーコンセプトの「HONDA DNA」の名のもとに、ボディ剛性は先代よりも大幅に上げられた。 エンジンは全てVTEC化された F18B型 1.8L SOHC VTEC、F20B型 2.0L SOHC/DOHC VTEC、ユーロR用の2.2L H22A型 DOHC VTECの3種類。ワゴンはオデッセイと同じく、F23A型 2.3L SOHC VTECがラインナップされる。ミッションは5段MTと4段ATのラインナップで、スポーティモデルにはSマチック付ATが組み合わせられる。 安全装備として、「SiR」にVSAと呼ばれる車両挙動安定化システムを標準装備されるほか、上位グレードのロービームにディスチャージヘッドランプが装備される。 7代目 (2002-2008年 CL7/8/9型) 
先代同様、同一のプラットフォームをベースに世界のマーケットのニーズに適したモデルを投入するコンセプトに変更はないが、日本仕様は欧州仕様と統合され、5代目以来の3ナンバーボディとなる。北米仕様は独自の設計となり、日本市場には後に4代目インスパイアとして登場する。日欧仕様アコードは、北米ではホンダの高級車ブランド「アキュラ」において、「アキュラ・TSX」として発売されている。 ボディタイプは4ドアセダンと5ドアワゴンのラインナップに変更はないものの、cd値が0.26と空力に優れ、パッケージングの見直しにより、全長、ホイールベースの大きな4代目、5代目モデルよりも居住性も向上している。シートの設計も全面的に見直され、運転席にはシュクラ製のランバーサポートが追加された。 HiDS(IHCC:インテリジェントハイウェイクルーズコントロール+LKAS:レーンキープアシストシステム)がオプションで装備できる。 エンジンは、新開発された前方吸気、後方排気のホンダ・K型エンジンで、アルミ合金ブロックを持ち、排気量別にDOHCの2.0LのK20A型と2.4LのK24A型の2種類がラインナップされている。連続可変バルブタイミング(VTC)を採用したi-VTECにより、全域で扱いやすいトルク特性となった。スポーツグレードの「ユーロR」用のK20A型は、高圧縮ヘッドをはじめ、ピストン、クランクシャフトなどのパーツの変更により、ピークパワーが向上している。組み合わせられるトランスミッションは「ユーロR」に6MT、その他のグレードにはSマチック付の5ATが搭載される。 同車として3度目の日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞し、同一車種の受賞回数としては同社のシビックの4回に次ぐ。国内のセダン・ステーションワゴン市場の減少で、2008年5月1日現在は平均4〜500台程度の販売台数に留まっている。 8代目 (2008年- CU2型) 
今回のモデルチェンジで、実質上1クラス上へ移行したインスパイアのポジションを埋めるためにアッパーミドルクラスへと移行。欧州市場での競争力を一層と高めるためにボディサイズも先代より一回り大きくなり、特に室内幅を拡大するべく、ボディを大きく拡幅した。肩やひじ周辺にゆとりを持たせ、フロントセンターアームの採用で先代を超える快適さを目指した。ドライブポジションは操作性と調整自由度を広げ、シートはホールド性とステアリング操作を考慮した形状となる。 専用の片側スポット溶接設備・工程を導入し、ルーフとピラーとの結合効率を向上させボディを剛性と静粛性を向上した。シャシーは低重心化を図り、高い運動性能と乗り心地の両立を図る。フロントピラーは4代目ホンダ・オデッセイと同様の構造を採用し、太さを18%スリムにすることにより視界の向上を図った。 安全面では、サイドカーテンエアバッグなど6つのエアバッグや、VSAと協調し車両の挙動を安定させるモーションアダプティブEPSを全グレードに標準装備している。併せて、自己保護性能と相手車両への攻撃性低減、歩行者傷害軽減を性能を従来より向上させたボディを採用した。 先代と同様に、高速道路での運転負荷を軽減する、ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール:先代のIHCC)をオプション設定し、LKASを一部グレードに標準装備した。 日本向け仕様は、エンジンを全車プレミアムガソリン(ハイオク)仕様のK24A型 2.4L 直4 i-VTEC(206PS)に統一された。グレード体系も「24E」・「24TL」・「24TL SPORTS STYLE」・「24iL」の4グレードで、FF車のみラインアップされる。 もともとは、2008年中に展開が予定されていた日本向けアキュラブランドへの移行準備のため現在販売されている8代目北米仕様アコード、すなわち日本でいう5代目インスパイアを日本でもアコードとして発売する予定だった。だが、日本での自動車販売台数低迷からアキュラブランドへの移行は白紙撤回されたため、インスパイア、アコードともそれぞれフルモデルチェンジを受けて現在に至る。 |